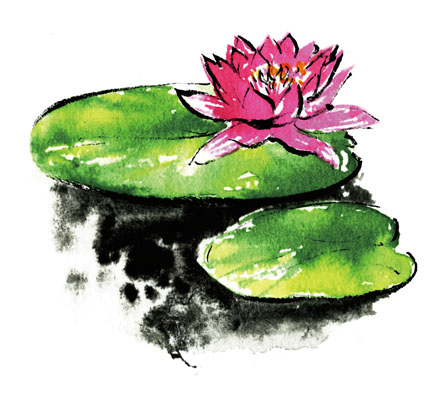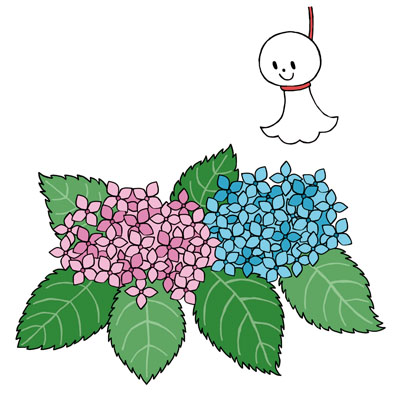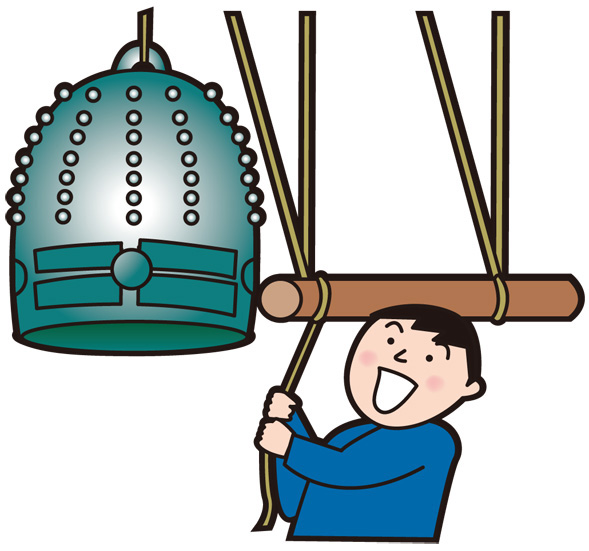日々の糧と法話
このページは老僧の私が少しでもみなさんに
仏さまの教えに親しんで頂きたいと作っているものです。
なむあみだぶつの教えを詳しく知りたいお方は真宗の各ご本山も法話を出して居られますし
真宗各派のご本山十派が真宗教団連合を作っておられます。各ご本山に属したお寺が
全国に沢山有りますので、是非詳しいお話をお聞きください。
お寺の場所が分からない場合はお調べもさせて頂きます。
それでは今日も日々の糧と法話をお読みください
◎ 愛は恵まれるものであって 買われるものではない。
◎ 与えられた仕事に興味を持って 全力を尽くす。・
◎ すぐに断るのは 約束をして長引かせるより良い。
◎ 仲の良い猫の群れは 仲間割れした狼より強い。
◎ 善を努力すれば 報い必ず将来にあり。
◎ 流れぬ水は腐り 磨かぬ玉は光らない。
◎ ひろげよう 心のぬくもり 人の世に。
◎ 仏にささげた浄財は やがて我にかえる。
◎ 本物は控えめ 偽物は大げさ。
◎ 甘い言葉には 裏がある。

一口法話
思い通りにならない世界
お金がもっと欲しいもっと欲しいという願いは、努力すればそれなりの叶えられる。
しかし、重い病気になって、なんでこんな病気になったのだろうと愚痴ってみても
病気は治らない。
また、まだまだ死ぬのは嫌だと思っても自分の歳を取る自由にはならない。
歳を取るのも嫌だと思っても、月日とともに否応なしに歳を取る。
老・病・死は人の思いを超えたものである。
それを忘れて、私の力で何とかしよう。何とかできると錯覚するから
苦しむのです。
人の思いを超えたものは、仏様にお任せするしかない。
大慈悲心の阿弥陀仏なればこそ。 たすかりようのない凡夫を
哀れみをもってお救い下さるのです。
なむあみだぶつ。なむあみだぶつ。
鷺澤顕昇師著日々のことば
法蔵館より借用
最近不平。不満の声が蔓延しています。色々問題があると思いますが
そこで上所重助と言う方の言葉を見つけました。
夏が来ると「冬が良いと」言う 冬が来ると「夏が良い」 と言う
太ると「痩せたい」と言う 痩せると「太りたい」と言う
忙しいと「暇になりたい」と言う 暇になると「忙しい方がいい」と言う
自分に都合が良い人は「善い人だ」と言い
自分に都合が悪くなると「悪い人だ」と言う
借りた傘も雨が上がれば邪魔になる。
金を持てば、親さえも邪魔になる
衣食住は昔に比べりゃ天国だが、上を見て不平不満の
明け暮れ 隣を見て愚痴ばかり
どうして自分を見つめないのか 静かに考えてみるが良い
一体自分とは何なのか
親のおかげ・先生のおかげ・世間様のおかげの固まりが
自分では無いのか
つまらぬ自我妄執を捨てて得手勝手を慎んだら
世の中はきっと明るくなるだろう
「俺が」 「俺が」を捨てて「おかげさま」 「おかげさま」で暮らしたい
不満が多くなると どんどん落ち込んでいく。 有難いと明るい生活を送りたいですね
なむあみだぶつ 合掌
◎ 親は子どもに財産を残すよりも 徳の遺産を残すのが良い。
◎ 天才は努力の先に 咲いた花です。
◎ たまには息を抜く それが生き抜く力となる。
◎ 知徳 報恩 受けた恩は石に刻み 恨みは水に流そう。
◎ あわあだしい 忙しい生活 何か忘れて居ませんか。 田村行良氏のことば
◎ いたわりは 物にも 人にも くさきにも
◎ 嫁ぐ子に 忘れず持たす 数珠一つ。
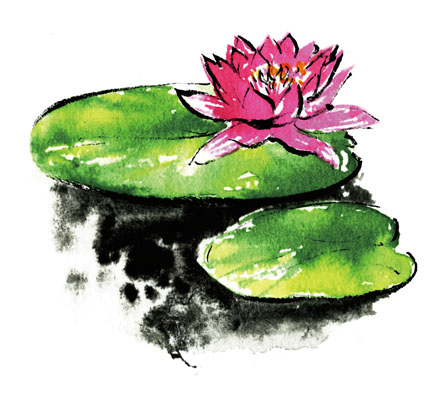
一口法話
この世は私がつくったものではない
だから 私の思い通りには ならぬのです
おしゃか様は「生きる事は苦であると お説きになられました。
そして、「生きることが苦しいのは執着する事である。
執着する事から目覚める(正しい智慧を持つ)と苦しみから抜けられる」と
お説気になられました。
私たちは、地位や財産に囚われ いつまでも失くしたくないと、
つかんで離さない。
しかし、諸行無常 、物事は常に移り変わっていくものです。
今有る財産や地位、そして、私の命も永遠に続くものでは有りません。
浄土の教えは、念仏のいわれをきくことが{執着する心から目覚める」
法であると教えられています。
思い通りにならないから苦しい だから思い通りにならないことに気付けよ と
教えて下さっているのです。
南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。合掌
◎ 十人の子を養う親がある 一人の親養わぬ十人の子あり 法句経
◎ 並みだと共にパンを食べた者でなければ 人生の味はわからない。 ゲーテ
◎ お金を貯めて自信を得ている人がいる お金が無くなればなくなる自信である。
◎ 死生を超越することは 宗教の真の目的である 夏目漱石
◎ おなじ太陽の下の旅なれど 曇る日も有り 晴る日もあり。 暁烏 敏
◎ 真実は 沢山の言葉を必要としない
◎ 鬼は世間では無く 私の中にいる
◎ 信心をつかむモノでは無い 仏さまにつかまれている事を喜ぶばかりです。
◎ 一度真剣に自分の生きざまを振りかえってみませんか。

一口法話
心に棲む三匹の鬼
心で造る罪である貪欲(とんよく)瞋恚(しんに)愚痴(ぐち)を
たとえた物が青鬼・赤鬼・黒鬼の三匹です。
青鬼は貪欲を・赤鬼は瞋恚・黒鬼は愚痴の心を表したものです。
鬼と聞くと、そんなものは迷信だ!。おとぎ話だと思うかも知れませんが
仏教で説かれる鬼とは心の中に棲む鬼です、
心の中がとても人には言えない事を思わせたり・恐ろしい事を言わせたり
恐ろしい事をやらせたりするのです。
心をしずめて、それぞれどんな心なのか。
自分自身の心の内側を覗いて見ましょう。
中々自分の心の鬼退治は難しいですね。
なむあみだぶつ 合掌
◎ 子どもと船は舵次第・親の笑顔が子にうつる。
◎ 人の値打ちは其の人の暇な時間とお金の使い方でわかる。
◎ 「幸福とは」有り難いと思う心の中に宿る。
◎ 暗闇の中で宝が有ってもつまずくだけだ。
◎ 世も末だと言う言葉が有るが、仏教でいう末法の事だ心がけたいです。
◎ 警察から警察だと名乗ったた電話がかかって来てもすぐに信用しないようにと大阪府警からメールが来ました。
◎天才であるより、いいひとで有る方がずっといい。 アンパンマン やなせたかしさんの言葉
◎ 全ての経験が、いつか自分の力になる。 PHP 梶 裕貴さんの言葉より
◎ 一緒に泣いてくれる人が有れば救われます。 豊島学由師のことば
◎ 南無阿弥陀仏は煩悩から離れられないと嘆く人を救うのが第一目的です。
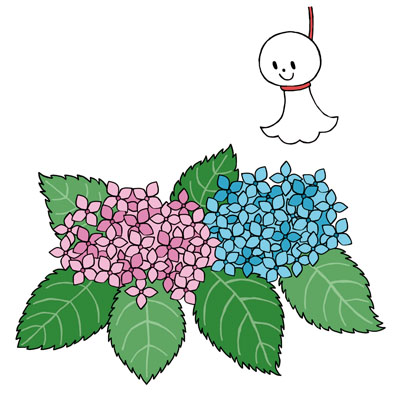
。一口法話
誰でも知っている事
昔、中国の杭州というところに、いつも木の上に座って静かに考え事をしているお坊さんが居りました。
その様子が丁度鳥が巣を作っているようだったので人々は”鳥の巣の禅師様と呼んでいました。
ある時、白楽天と言うえらいが訪ねてきて、禅師様に聞きました。
「あなたは尊い仏さまの教えを説いておられるそうですが、一体仏さまの教えの極意とはどういう事ですか」
いつものように気の上に座っていた禅師は,すぐに答えました。
「仏さまの教えを一口で言うと悪い事をしない・善い事をする。正直にする。この三つです」
わざわざ訪ねて来た白楽天は「な~んだそんなことか。そのくらいのことなら三歳の子どもでも知っている」と
少し馬鹿にして言いました。
鳥の巣の禅師は、声を荒くして「三歳の子どもでも知っているこの事が、八十・九十になっても
正しく行える人はいないのです!」と諭されました。
賢い白楽天は強く胸を打たれました。
私たちはどうでしょう。あれもしてやったのに、これもしてやったのに、
それにあいつは!!と言う心は起きませんか?。
「恩知らずが」の気持ちは起きませんか? 「受けた恩は石に刻み・恨みは水に流せ」と言う言葉がありますが
中々難しいですねぇ
小さなことでもイイ 見返りを求めない良いことを始めませんか。

◎ 一切の有情は みなもて世世生々の父母兄弟なり 歎異抄
◎ いつくしみこそ 心のゆとり。
◎ 美しい笑いは 家の中の太陽である。
◎ 宗教無き教育は 賢い悪魔を作る。 ウェリントン
◎ 蒔いた種は 遅かれ早かれ芽を出す。悪因悪果・善因善果
◎ 仏さまのお心は 大慈悲心です。
◎ なむあみだぶつ それは私の親の名 まかせなさいっと親が私を呼ぶ声。
◎ プラスの3K 希望 工夫 感動。
◎ 穏やかな顔と優しい笑顔は お金や物がなくても出来る布施の行です。

一口法話 生かされて生きている私
太陽や大地や水の恵みを受け
お米やの命をいただき
生かされて生きている私
お米や魚やお肉を食べると言う事は、おこめや魚など動物の命を頂くと言う事。
ほかの生き物の命を犠牲にして、自分が生かされている。
その食べ物は、太陽や、水や、空気や大地のおかげで育つ事が出来た。
だから、内から何まで宇宙万物一切の恵みを受けた
そのおかげさまで私はいま生かされています。
しかし、普段は其のこと忘れてしまっている。
与えられている命を「我が命」を生きていると錯覚している。
この命は私のものでない、宇宙万物のいのちなんだ。
その事に気づき感謝する気持ちが南無阿弥陀仏

何かで見掛けた言葉
自分に都合がいい人は「善い人」だといい 自分に都合が悪くなると「悪い人だ」と言う
借りた傘も、雨があがれば邪魔になる
金を持てば親さえも邪魔になる
衣食住は昔に比べりゃ天国だが 上を見て不平不満の明け暮れ愚痴ばか
隣を見ては愚痴ばかり
どうして自分を見つめないのか考えてみるがよい
一体自分とは何なのか
親のおかげ・先生のおかげ・世間様のおかげの固まりが自分ではないか
つまらぬ自我妄執を捨てて得手勝手を慎んだら
世の中はきっと明るくなるだろう
「俺が」「俺が」を捨てて「おかげさまで」「おかげさまで」と暮らしたい。
上所重助さんの言葉は仏教の四恩の精神から出た言葉だと思います。
四恩とは今の言葉で言うと 社会の恩・親の恩・師匠の恩・仏さまの恩ですが
中々恩を感じさせないのが煩悩のはたらきでしょう。
怒り・ねたみ・そねみを三毒の煩悩と言って満足感謝の心を失って自分自身の心が自分を苦しめるのです
その私の姿を見て必ず救う救いたいと願われている仏さまに感謝の合掌をさせて頂きましょう。
なむあみだぶつ・なむあみだぶつ合掌

◎ 他人の悪口はウソでも面白い 自分の悪口は本当でも腹が立つ。
◎ 人は欲に目がくらんで 正しい判断を失う事が多い。
◎ 美しい物を美しいと思える 貴方の心が美しい。
◎ 悔いが残らないように 今を大切に生きよう。
◎ ありがとう と 言われるように言うように。
◎ 腹を立てることで 得なこてゃなにも有りません。
◎ たとえ質素な暮らしでも 心は豊かでありたい。
◎ 自分の自慢を 喜んで聞いてくれる人は少ない。
◎ 幸福と感じるか 不幸と感じるかはあなた自身です。
◎ 物の不足した頃には 心の豊かさが有り 親子の間にも温もりが有った。
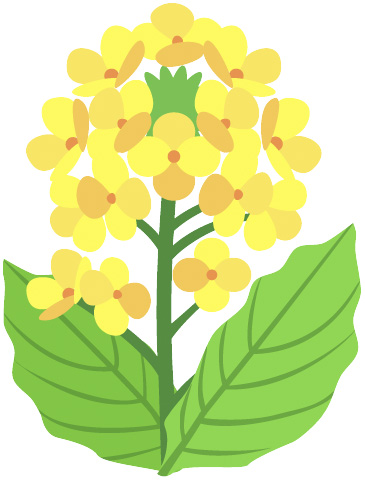
一口法話 お か げ さ ま
「おかげさまで 元気にやっております」 よく挨拶ぬ使う言葉です。
「かげ」に「お」と「さま」をつけて尊敬している。
「かげ」と言うのは眼に見えないものです。
その見えないものに感謝しているのです。
では「かげ」と言うのは何でしょうか
私たちが毎日食べているお米は、農家の人が田植えをして、肥料をやり。
雑草をとり、初めて収穫できるもの。 農家の人のおかげです。
しかしそれだけでは有りません。
太陽の光も必要ですし。水も空気も必要です。
それらの眼に見えない大きな力が働いて私達の食料となるのです。
眼に見えない働きの感謝する言葉 それが「おかげさま」
手を合わせて「いただきます」と感謝して合掌させて頂きましょう。
なむあみだぶつ合掌

それでは今日も日々の糧と法話を読んで頂きます。
◎ 自分が絶対だと思っている間は、仏の世界に入れない。
◎ 見えそうで見えないのは、自分の短所と欠点です。
◎ 悲しい時は泣くもよし 仏さまが涙を拭いてくださいます。
◎ 苦労も困難もなければ、本当の楽しみもない。
◎ 先祖は生のはじまりであり、 父母は形の始まりです。
◎ 人の心の休まる所、それは家庭です。
◎ 待は長くして 過ぎ去れば短き月日です。
◎ 眼が覚めたら 今日の命にまず感謝をしよう。
◎ 物を頂くなら くださるお心も共に頂こう。
◎ 臨終は人生の卒業式 お浄土の一年生。

一口法話
お か げ さ げ さ ま
「みほとけの み教えを聞くものは、心に温かさを 言葉に美しさを
態度に 明るさを持ちます。 妙好人の言葉
「言色つねに和して あい慰房(いれい)することなかるべし」 (無量寿経)
私達はいつでも、どこでも、誰にでも、心豊かに有りたいと思って居ます。
けれども日々の事柄を静かに考えてみると、なかなかそうばかりはいかないようです。
笑顔でニコニコしているような時でも、心のちょっとしたひっかかりで
急に苛立たしい気持ちになる。
そんな事を私達はよく経験します。
厄介なことに、このような気分はたちまちにふくれあがって顔をこわばらせ
心や身体ノバランスを無くし、私達の心を貧しくしてしまいます。
そんなに「かたくな」にならずにちょっと身体の力を抜けばどんなに
楽になるものと思うのですが・・・
このように、腹を立てたり、欲を起こしたり、取り留めもなく迷いにとらわれる心を
仏教では煩悩(煩悩)と言ってます。
この煩悩が働けば働くほど、私達は物事の本当の姿を見失ってしまいます。
心が澄み切った水のように清らかですと、ものごとをありのままの正しく写しだします。
反対に、自分の都合ばかりを考えているような心はわがままで、濁っています。
その濁りに邪魔されてどんなことも、ありのままに写し出すことが出来なくなるのです。
有難い・勿体ない・すみませんの心を開発すれば本当に幸せな気持ちになれるのですが
中々難しいですね。一歩前に進んでみませんか。 合掌 なむあみだぶつ

◎ 明日と言うより今日を大切に。
◎ 私はおしっこが出なくて亡くなった人を知っている。おしっこが出てくれることは当たり前ではない。
◎ 私はウンチが出なくて亡くなった人を知っている。ウンチが出てくれることは有り難い。
◎ 当たり前と思って居る事は本当は幸せな事なんだ。当たり前に感謝をしよう。
◎ 仏さま・ご先祖様に感謝する、その心から幸せが始まる。
◎ 昔の人達が持って居た有り難い・勿体ないの心がどこに行ったのだろう。
◎ お金の為なら平気で人をだます・金を奪う・人を殺す。餓鬼・畜生・地獄の世界。
◎ ありがとう、言われるように言うように。感謝の気持ちが心を豊かにする。
◎ 朝の来ない夜はない。前向きに考えて行こう。
◎ たった一言が人の心を傷つける・たった一言が人の心を傷つける。心掛けたい事ですね。

一口法話 和 顔 愛 語 (わげんあいご)
荒々しい言葉は先に毒の付いた矢のような物で人の心を傷つけます。
矢を放たれると相手の心臓にブスリと刺さって抜けなくなります。
矢の先に塗られた毒が全身にまわり殺してしまう。
もし相手が死なずに生き返ったら、ガードマンを雇わないと今度は自分が殺されかねません。
賢い人は、多く語りません。極めて控えめな言葉を使って心に残ることを言います。
トルストイは「手よりも むしろ舌により多くの休息を与えなさい」と言う言葉を残しています。
素晴らしい忠告です。
一度発せられた言葉は本人が忘れてしまった後までも残って生き続けるからです。
人には、優しい言葉、思いやりのある言葉を持って接して行きたいものですね。
お経の中に和顔愛語(和顔愛語)と言う言葉が書かれています。

◎ 朝のない夜は来ない。
◎ 子どもは親の鏡です いつの間にか親が手本になっている。
◎ 合掌は家庭教育の基本です 合掌は感謝の心を表す姿です。
◎ 文句が多すぎる 自分で作れぬ物で生かされています。
◎ 丸い心こそ仏の心 心安らかな一日を。
◎ 人には厳しく 自分には寛容な人が多い。
◎ 生きてます 生かされていますこの命
◎ 一に合掌 二に礼拝 三に感謝で家庭円満。
◎ 「おかげさま」と言える人生に 孤独はない。
◎ 今日一日ニッコリと 今日一日シッカリと。

一口法話 出 遭 い (であい)
一人の人間が生まれて死ぬまで、一体どれくらいの人との、あるいは人に限定しないならば
どれだけの数の出遭いがあるのでしょう。
しかし一生のうちに、自分自身と出会える人はどれほどあるでしょうか。
以前、大阪の池田の小学校に男が乱入し多くの児童や教員を殺傷すると言う事件が有りました。
楽しい所であるはずの小学校で刃物を持った男に追われ傷つけられ、殺された子どもたちの
恐怖はいかばかりであったでしょう。
それをお思えば心が痛みます。
この事件の容疑者が、この学校を選んだのは、自分自身がかって受験に失敗しいる
ことへのコンプレックスが有ったようですが、元々経歴詐欺や学歴詐欺を繰り返していた
と言う報道が有りました。
人間だれしも虚栄心は持って居るものでしょう。そして、自分の至らなさ?コンプレックスを
バネとして成長することも有るでしょう。
しかし、この容疑者の場合、本当の自分を直視せず自分の作り上げた虚栄とのギャップを
埋める方法として、ねたみ、嫉み、と言う最悪の手段を選んでしまったのではないでしょうか。
しかしながら現代の風潮は如何でしょう。政界バトルとか熟女バトルと称して他人のもめ事を
はやしたて、そのくせ流行は癒し系、自分本位で無責任と言う点では、凶悪犯罪に到ることは
なくても心根は同じようなものでは無いでしょうか。
かって自分自身に落胆し悩む一人の青年がいました。
その青年は、次のように自分を評しました。「悲しい事に私は愛欲の世界に溺れ、名誉欲や財産欲の
世界に迷い込み、救いの手を差し伸べられても喜べず、真実の世界に近づく事を快く思えない。
恥ずべきことだ、傷むべきものだ」と
けれども彼の場合「誠なることにこのような私を救い、決して見捨てはしないと言う世を超えて、
稀な正しい教えに出会えたのだから、よく聞き、それを思い、遅れを取るまい」というように
本当の自分に出遭い、誠なる教えに出遇う事が出来ました。
その、彼の前に広がった世界は「慶こばしいことに私は今尊い教えに出会えた。
このご恩の深い事を思い聞いたことを慶び獲たものを讃えよう」と言うものでした。
この青年は親鸞聖人で、出会えた教えは南無阿弥陀仏の教え、そして讃えて説かれたのが
浄土真宗の教えでした。
自分を見失い感謝を忘れた現代は物質的に少々満たされても、でるのは不平不満ばかり、
おまけに何かに怯え疲れ果てて居ませんか。
「私は願われている」という自信のもと、慶びと感謝の生涯をおくられた親鸞聖人に学びたいものです。
これは、大阪市の正信大等さんが2002年に投稿されて物ですが、現在を返って見てどうでしょうか
仏教は古くさい地獄極楽なんてあるもんかと言う風潮が流れましたが、
実際に いま大学生が殺人強盗をしたり中学生や高校生が強盗を計画したり、詐欺事件も多くなりました。
そして、不平不満ばかりの世の中になりました。仏教でいう末法の姿です。
いま一度振り返ってみて合掌して有難うございますと感謝の気持ちの持てる身になりたいものです。
合掌 なむあみだぶつ

◎ 帰る世界(お浄土)が有るから安心して人生を送れるのです。
◎ 優しい言葉と笑顔で感謝(和顔愛語)の和らぎの世界。
◎ 傷つけられたことを覚えていても傷つけたことを忘れている人が多い。
◎ 言われたことは覚えていても 言うたことは忘れている。良い事も悪い事も。
◎ 不要なものを手放せば 残ったものの有難みが分かる。
◎ 一番お不幸は 今有る幸せに気づかない事。
◎ 知りながらつい忘れがち親の恩。
◎ ご先祖さまは父方だけではない 母方にもご先祖さまはいらっしゃる。
一口法話 育 て る 心
花や野菜を育てるのには、チッソ・リンサン・カリなどの肥料や
水や太陽の光が必要です。
また植物を大切にする思いやりの心も必要です。
人を育てるのにも食料や学習環境、生活環境も必要だし
学問知識も必要だが、もっと必要なのは人を思いやる心です。
だから、子どもを教育する場に布施(ほどこし)感謝(ありがたさ)
同朋心(みんな仲良し)など仏教的な心を取り入れたいものです。
何かの本で読みましたが、アメリカの精神心理学者が今警告を鳴らしています。
褒めて育てることは大事ですが、褒められる事だけで育った子どもは
環境に順応できないこどもやおとなが多いそうです。
叱る事・注意する事・教える事と怒る事は違います。
怒ろ時には自分の感情が入ります。
環境に順応できる事は大事です。
笑顔で優しい言葉がかけられる大人になれるように育てたいものです。合掌

◎ 手を合わせ感謝の気持ちで暮らしましょう。
◎ 麦は寒さに耐え、米は暑さに耐えて実ります。あと少しです。頑張りましょう
◎ 世の中は百の善言よりも一つのウソで崩れる。
◎ 命を見つめる 木の命を 土の命を 生き物の命を 人の命を
◎ 生かされている命に感謝して手を合わせましょう。
◎ 人の頭の冠よりも、自分お足の裏を褒めてあげたい。
◎ 苦労も困難も無ければ、本当の楽しみもない。
◎ 目が覚めたら 今日の命にまず感謝しよう。
◎ 罰や祟りを押し付ける宗教には先ず間を置こう
◎ 見えそうで見えないものは、自分の短所と欠点です。

一口法話 当 た り 前 で 無 い い の ち
令和六年の元日、みんながお祝いで楽しんでいる時、突然、能登半島を中心とした
大地震が起き非常に大きな災害となりました。多くの家屋が見る影もなく崩れ、多くの方が亡くなったり
ケガをされたり 大変な事でした、そして続けて大きな地震が各地で起こり加えて猛暑。酷暑となり
更に大きな台風に加えて豪雨に見舞われました。
私は、大阪に住んでいますので「大阪は自然災害の少ない所で有り難いですね」と言う声を
よく聴きますが決して他人事ではありません。南海トラフの地震が来る予報も出ています.
富士山が爆発して火山灰が30センチ積もると想定されると、新聞で報道されています。
毎日当たり前のように生活を送って居ますが「当たり前」などないのです。
今日の一日が、あらゆる不思議なご縁によって生かされているのです。
その中で私を支えて下さっている人々や生き物(食べ物)のいのちにどれだけ感謝しているでしょうか。
いや、むしろ不平不満の毎日ではありませんか。
「南無阿弥陀仏は」ご先祖さまや死者の霊を慰める呪文やまじないではありません。
「たとえ、いつどんなことが有ってもあなたを私(阿弥陀如来)の国(浄土)に仏の【いのち】と
生まれさせたいという阿弥陀さまの願いが声となって届けられているのです。
その声に「ありがとうございます」と阿弥陀如来さまのお名前を(南無阿弥陀仏)と呼ぶのが
浄土真宗のお念仏であります。
阿弥陀如来さまに願われた「いのち」であったと気付かさせていただき、一日一日感謝の日暮らしを
贈ることが大切な事であります。
仏さまとなられたご先祖や亡き方の願いは、念仏もうす身になって下さいと言う願いなのです。
minori ホームページ参照
◎ 麦は寒さに耐え、米は暑さに耐えて実ります。
◎ 命を見つめる。気の命を・土の命を・人の命を。
◎ 感謝で暮らす生活には、不幸の入る余地がない。
◎ 人生は二度ない・しかし出直す事は出来る。
◎ 先祖を粗末にすれば、いずれ自分も粗末にされる。
◎先祖をよく敬う人は子孫の事も考える。
◎ ロウソクは 身を炎にして暗い闇を照らす。
◎ 和顔愛語。 おはよう。有難う。ご苦労さま。すみません。
◎ 生きているのではなく、大きな力で生かされているのです。
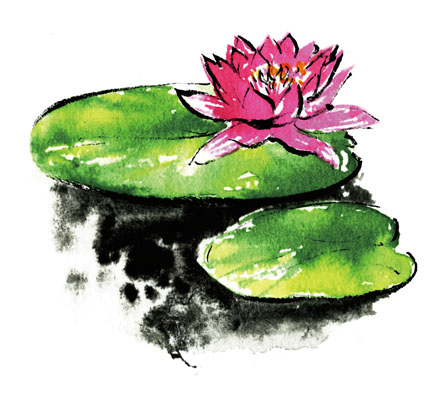
一口法話 ほ ど こ し (布施)。
布施 ふせと言うとお寺さんに包むお礼のお金のように思って居られる方が多いようです。
確かにそれもお布施です。
本来布施と言うのは修業の一つで布施の行と言います。
布施の実践に当たってはいささかの我執が有ってはならないと言われています。
仏道修行をされるものに敬いを持って物資を施し。仏道修行を行う者は教法を施す。
これがいわゆるお布施の始まりです。
施すものは施したという思いや、施す物について惜しみや誇りがあってはならず
また受けるものも多い少ないの心を動かしてはならぬと戒められています。
金銭や物質的な物のみが布施の対象になるのではありません。
無財の七施と言って「優しいまなざしをほどこす」 「優しい言葉」で生活が明るくなります。
「和やかな顔」 「温かい心」 「身体を施す骨身惜しまず相手の為に働く」
「宿を施す。どんな客でも気持ちよく迎える。金持ちの家でも冷たい家が有り、
貧しい家でも暖かい家が有ります。最後に「床座施席を譲る」
以上を無財の七施といいます。
おしゃか様が人間の心に純なるものを求めて
布施の徳を高調せられた尊い慈悲の心が偲ばれます。
布施の得は随喜のこころで驕慢を離れさせるので有って、
捨てがたい貧しい心をすてさせるものなのです。自分お出来る事から
明るい社会を作るために
改めてお金や物がなくても出来る布施の行・「無財の七施」を実行しませんか。

◎ 親や先祖を粗末にする人はやがて自分も粗末にされる。
◎ 過ちは素直に詫びて改める事です。言い訳すればするほど事が大きくなります。
◎ 全く欠点の無い人はいない唯欠点をいつまでも欠点では成らない。
◎ 明るさ(微笑み)を心にも顔にも言葉にも。
◎ 子どもは親の言うとおりに歯ならないが、親のする通りにする。
◎ 裕福な家庭の中には時には愛の無い家が有る。
◎ 貧相と言う事は 心がいつも腹立っている事です。
◎ 不幸のどん底では遣り損ないはないが、幸福の頂上では踏み外すことが有る。
◎ 死すべき命 今日有るのは有り難い。

一口法話 いただきます ごちそうさま
昔、京都の嵐山の有名なお寺の子どもさんが、小学校1年生になり初めての給食の時
何時もの通り両手を合わせて「いただきます」と言ったら、
先生から「学校に来てそんな事はしてはいけません」と注意されたそうです。
家に帰った子供さんから聞いたお父さんが不思議に思って先生に事情を聞きに
行かれたそうです。若い先生は「教育基本法で公立学校では宗教教育をしてはいけないんだ」と
言われたそうでです」
確かに教育基本法には公立学校では、
特定の宗教教育その他宗教的活動はしてはいけないと書いて有ります。
しかし、教育基本法第9条(宗教教育)をよく読んでみると、まず最初に
(宗教教育)『宗教に対する寛容な態度及び宗教の社会生活における地位は
教育上これを尊重しなければならない』とあります。
若い先生はこの条文をきちんと読んでなかったのかもしれませんね。
昔から頂きますご馳走さまその気持ちを表す動作それが合掌です。
以前、外国に行かれた方が、その国の言葉がしゃべれないので、
感謝の気持ちを持って合掌して頭を下げたら気持ちが相手に通じたと言われてました。
すなわち合掌して頂きますと言うのは
相手にたいしても、食べる食べ物に対しても感謝の気持ちを表しているのです。
永六輔さんは、自分自身の著作の中で、
有る小学生の親が「給食代を払ってるんだから、
子どもに『いただきます』といわせるのはおかしいのではないかと
申し入れたことに対して「僕達が食べるものはみんな【いのちです】
その【いのち】を食べるのですから、あなたの【いのち】を私の【いのち】に
させて頂きますと言うのです」と応えられています。
私たちは当たり前と考えているは当たり前ではないのです。
一切れのお肉は牛一頭のいのちなんです。感謝して頂きましょう。

◎美しい花が咲くのには目に見えない根の働きが大きい。
◎ 他人の悪い所はよく見えるが 自分の悪い所には気が付かない。
◎ いだかれてあるとも知らずおろかにも われ反抗す大いなる手に 九条武子
◎本願を信じ 念仏申さば仏に成る。
◎ 病気になって初めて健康の有難さを知る。
◎ カーナビは便利だが、たまに一方通行を逆に案内することが有る。
◎ 温故知新 古きを訪ねて新しきを知る。
◎ 今日と言う一日は二度とない一日です。
◎ 十人の子を養う親あり 一人の親を養わぬ十人の子あり。

一口法話 わかっちゃいるけど やめられない
志村けんさんが所属していたドリフターズと言うコメディグループが有りましたが、
その前に一世を風靡したハナ肇とクレイジィキャッツと言うコメディバンドが有りました。
メンバーの一人で植木等さんとい方が居られましたが、
番組の中では(当時としては)悪ふざけとと見られる破天荒な芸で、知識人から
知性の欠片もないと酷評され毛嫌いされていたようですが、実際はこ超真面目な方でで
この植木さん家庭に帰るとお寺の息子さんだったせいか、厳格な威厳のある方だったそうです。
大ヒットした曲の「スーダラ節」を歌う話が来た時も、自分の人生が変わってしまうと悩まれたそうで
実家のお寺、浄土真宗のお寺の住職だったお父さんに相談されたそうです。
お父さんは気骨のある立派な方で戦争中戦争反対で。出征する若者がお寺に挨拶に来ると
「死ぬなよ・絶対生きて帰って来いよ」といわれたそうですが、このお父さんに相談された時に
「スーダラ節」の「わかっちゃいるけどやめられない」の歌詞は浄土真宗の親鸞聖人の
教えそのものだと応援されて初めて植木等さんは歌う決心をされたそうです。
と言うのを何かで読んだことが有ります。
「スーダラ節」がどうして教えに叶っているかと、よく考えてみると煩悩から離れようとしても
離れられない私、その私を助けて下さるのが南無阿弥陀仏のほとけさまなのです。
自分の力で煩悩を断ち切る事が出来るなら阿弥陀様は必要ありません。
わかっちゃいるけどやめられない。分かってはいるけど煩悩から離れられない私のための
南無阿弥陀仏なのです。

◎ お金より大切なものを見つければ人生は豊かになる。
◎ 有難いと思う心の中に幸福が有る。
◎ 親は子に、財産よりも 徳の遺産を残すが良い。
◎子どものために残した遺産で、子どもたちの争いの素になったのを何度も見てきました。
◎ 富士山には駆け足で登れない。
◎ 支出は必ず収入以内ですることです。
◎ 暗闇の中では、宝が有ってもつまづくだけだ。
◎ たった一つのふくれ顔が家庭を暗くする。
◎ 仏心者大悲是(仏さまのお心は大きなお慈悲の心です)
◎ お仏壇のお掃除は、自分の心のチリも取れる。

一口法話 あ り が た い
変な話で恐縮ですが、友人のお父さんが亡くなられてお通夜に行ってお供養と言って
少々お酒をよばれたせいか、家に着くなりトイレに入って小用をなした。
勢いをついて出てくる小便を終わってホッとしてトイレから出る時にふっと立ち止まった。
いつもなら”ああいい気持ち”と思わず出てくるところだが、今日はいつもとは違う。
お通夜の席で亡くなったお父さんの死因を聞いて来たからだ。
友人のお父さんは数日前に急に小便が出無くなり、入院して管を通して排尿したが、
期待する程もでず、その上尿に血がまじっていた。
そうするうちにも、尿が体内に廻り尿毒症を起こして全身が水膨れとなり、くちびるまで
腫れあがって来た。
人工透析手術するにも高齢の為不可能との事。やむなく腹膜透析と言う手術をしたが
残念ながら、二日ほど苦しんで亡くなったそうです。
その事を思い出して小便はしたくなったら出るのが当たり前と思って居たが、そうでは無かった。
そう気が付いた時、私は立ち止まってしまったのです。 有難い。そうだ有難い事なんだ。
私達は、自分で生きているつもりでいたが、大きな力に生かされて生きていたんだ。
私達は毎日の生活に慣れきってしまうと、お陰様と言う事を忘れてしまい、あらゆる事に
不満をいだき、愚痴をこぼす。そして、今、大きな力に抱かれてある事に気が付かないのです。
眼を開けばあたりまえであることが、驚きとなる
眼を開けばどこにでも教えがある
これは私の先輩である中西智海師の言葉ですが、心の眼の角度を変えて何事も見ると
当たり前では無かった、有り難い事だと全てに感謝させて頂けるでしょう。感謝させて頂く
日々を送りたいものです。合掌 なむあみだぶつ。 なんまんだぶ。

◎ たった一言が人の心を傷つける。たった一言が人の心を暖かくする。
◎ 有難う・すみませんの一言は人の心を暖かくする素敵なパワーを持って居る。
◎ お念仏「南無阿弥陀仏」は亡くなった人に唱えるまじないでは有りません。
◎ 南無阿弥陀仏は私達を護りお救い下さる仏さまに感謝の言葉です。
◎ ウンコが出てくれた・オシッコが出てくれた。有難い嬉しい 退院して帰ってきた方の言葉です。
◎ 雑草うと言う名の名前の草はない。害虫と言う名前の虫もない。
◎ 人と比較するところから不幸ははじまるのよ サザエさんの言葉
◎ 亡き人が迷っている と 言うその人が迷っている。
◎ 不満はストレスの素よ 感謝はエネルギーになるのよね。 森光子さんの言葉
◎ 世の中の乱れは自分さえよければ良いと言所から始まっている。

一口法話 許されて生きる
ある時、何人かの人が集まって、知っていて悪い事をした者と
知らぬ間に悪い結果を招いたものとどちらが罪が深いかと言う事になった。
勿論、知ってやった者の方が罪が重いと言う事になった時、ひとりが悪い事と事知って
悪いいことをした者は
悪い事をしたという自覚が有るから、いつか懺悔して詫びることも出来るが、
悪いと知らずに行ったものは、悪い事をしたと言う自覚がないから、反省し、懺悔することもないし、
詫びる事もないから罪が重いと思うと言った。
そこで、思い出したのが、先日NTTの関係の仕事をしている人の話です。
その人が、ある所で電信柱に上って工事をしていた時、電柱の傍で遊んでいた男の子に
母親が、「遊んでんと宿題せなあかんで」と言うと、その子は「宿題あれへん」と言う。
するとその母親が「宿題なかったって勉強せなあかん」と言った。それは母親としては当然のことで
母親の言う事も一理あるが、その後が悪かった。子供に勉強させたい一心からか、
「今、勉強せえへんかったら大人になってから(上を見上げて)あのおっちゃんように高い所に上って
仕事をせんならんようになるで」と言ったそうだ。
その子が高い所が嫌いな子だったかも知れませんが、電柱の上の人にとっては大きな侮辱である。
その人はムカッと来て下へおりてドナリ付けようかと思ったがNTTの看板が有るから辛抱したけど
腹が立って、腹が立ってと言う事である。
私たちは、知らず知らずのうちに、人の恨みをかうような色々な罪深い事を行ってきている。
罪深い 私であると気づかさせて頂いた時、許されて生きている私、。
生かされて生きている私であったと、お詫びと喜びで日々を送らせて貰いたいものです。
合掌
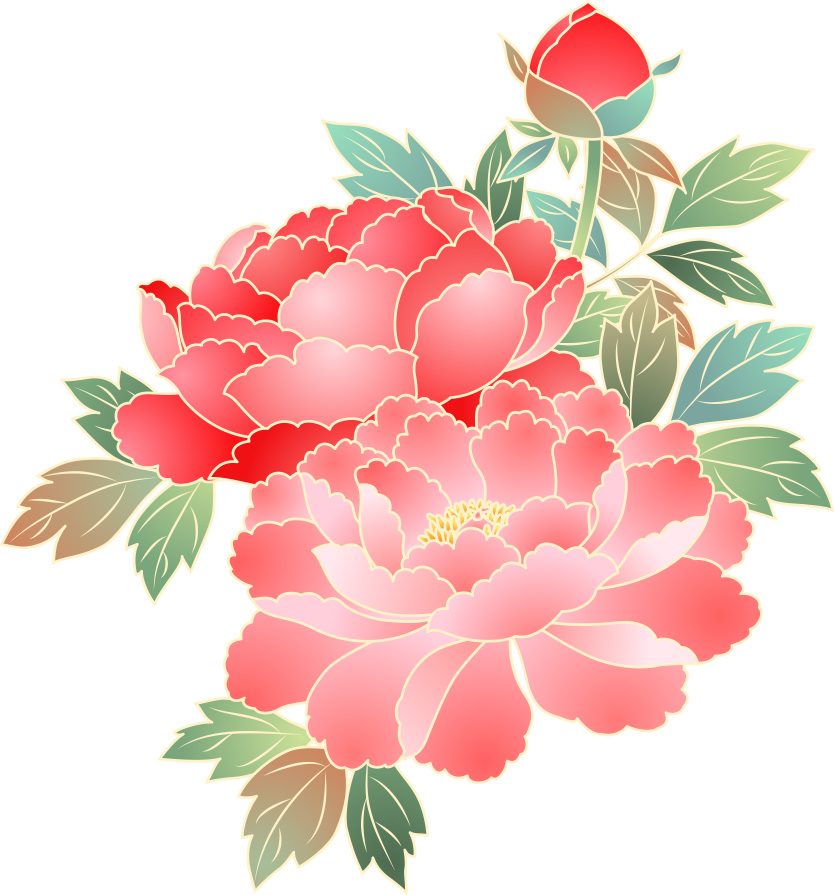
◎ 花を見る人は花から見られている 仏を拝む人は仏から拝まれている。
◎ こどもを信じて見守る愛情。
◎ 子どものしつけは家庭から。
◎ 手を合わせ心を合わせて 幸せに。
◎ 食事の時「いただきます」と言うのはと言う事は命を口にさせて頂きますと言う事です。
◎ 一本の野の花も精一杯生きている。私達も今日一日をどう生きるかです。
◎ 本当の物が分からないと偽物に騙される。
◎ 仏も餓鬼も畜生も私の心の中にある。どれをさせにするかが大事です。

一口法話 太陽や大地や水の恵みを受け
お米や魚など生き物の命をいただき
生かされて生きている私
お米や魚やお肉を食べると言う事はお米や魚など生き物の命をいただくと言う事。
他の生き物の命を犠牲にして、自分が生かされている。
その食べ物は、太陽や水や空気や大地のおかげで育つ事が出来た。
だから何かなら何まで宇宙万物一切の恵みを受けた、そのおかげさまで私は生かされている。
しかし、普段はその事を忘れてしまっている。
与えられている命を我がものとし「我が命」を生きていると錯覚をしている。
この命は私の物では有りません。 宇宙万物の以日なのです。
そのことに気づき、感謝する気持ちが、南無阿弥陀仏

◎ 外国で言葉が分からないので合掌したら通じた。これ世界共通語だった。
◎ 失って気が付く「当たり前」の有難さ。
◎ 財宝に富むと言えども 足る事を知らなければ心貧しい。
◎ 雑草と言う名前の草はない 害虫と言う名前の虫はいない
◎ 墓参り合掌した手で蚊を殺す
◎ 負けたことが有ると言うのが いつか大きな財産となる
◎ 人と比べる所から 不幸は始まる
◎ 亡き人が迷っていると言う人はその人自身が迷ってる。
◎ 不満はストレスの素よ 感謝はエネルギーになるのよね。 森光子さんの言葉
◎ たとえすべての事業財産を失う事がっても他力安心の信心を失ってはならない。
初代伊藤忠兵衛さんの言葉 (伊藤忠商事 丸紅の創業者)

一口法話 『当たり前でないいのち』
阪神淡路大震災・東北大震災・につ続いて元旦早々の能登半島の大震災。重なる災害に見舞われています。
「大阪は自然災害の少ない所で有り難いですね」と言う声をよく聴きますが、決して他人事では有りません。
日本は安全な所などないのです。又南海トラフなどと言う言葉もよく聞きます。
毎日あたりまえの様に生活を送って居りますが『当たり前』などないのです。
今日の一日があらゆる不思議な縁によって生かせれているのです。
その中で私を支えて下さっている人々や生き物(食べ物)の{いのち}のどれほど感謝しているでしょうか。
いや、むしろ不平不満の毎日ではありませんか?
「南無阿弥陀仏」はご先祖や死者の霊を慰める呪文やまじないではありません。
「たえいつどんなことがっても、貴方を 私(南無阿弥陀仏)の国(浄土)に仏の<いのち>と生れさせたい」
と言う阿弥陀如来さまの願いが声となって届けられているのです。
その声に「ありがとうございます」と阿弥陀如来さまのお名前(南無阿弥陀仏)を呼ぶのが
浄宇土真宗のお念仏であります。
阿弥陀如来さまに願われた「いのち」であったと気づかさせて頂き、一日一日感謝の日暮らしを送る事が
大切な事であります。
仏さまとなられたご先祖や亡き方々の願いは念仏申す身になって下さいと言う願いなのです
MINORIホームページより
◎ 有り難いと思う心の中に幸福が有る。
◎ 心よき笑いは家庭の太陽です。
◎ 宗教無き教育は賢い悪魔を作る。
◎ 不正直者は一時は成功したように見えるが、やがて化けの皮がはげる。
◎ 暗闇に中で宝物がっても つまずくだけだ。
◎ 四葉のクローバーを探すために 三つ葉や名もなき花をふんではいけない。
◎ 柔らかい枝は折れない 柔らかい心も折れない。
◎ 煩悩は本当に喜こべることを喜べなくする。
◎ 子どもに物や金で財産を残すと、もめごとの素になる。子どもには親から受け継いだ徳と言う財産を残そう。
、
◎ 感情をぶっつけるのが「怒る」 相手を良い方向に導くのが「叱る」混同していませんか。
一口法話 福の神と貧乏神
有る家に、一人の美しい女性が着飾って訪ねてきました。その家の主人が「どなた様でしょうか?」
と、尋ねますと、その女性は「私は幸福を与える福の神です」と答えた。
こで主人はろこんで、その女性を家に上げて手厚くもてなしました。
そのすぐ後から今度は、粗末な身なりをした醜い女性が入ってきました。
主人が「お前は誰だ?」と尋ねますと、その女性は「私は貧乏神です」と答えました。
主人は驚いてその女性を追い出そうとしましたところ、その女性は「実は、先ほどの福の神は私の姉なのです。
私達姉妹はいつも離れた事は有りません。
ですから、もし私を追い出せば姉もいなくなりますよ」と言いました。
その女性が去って行くと、その言葉通りに、あの美しい福の神も消え去って行きました。
これは『仏教聖典』と言う本に載っていたお話ですが、全くその通りだと思いませんか?
善い事も有れば、悪いことも有る。幸いも有れば災いも有る。
それが、私たちの人生だと思われませんか?
善い事ばかりの人生も無ければ、悪い事ばかりの人生も有りません。
ですから、少し良い事が続くからと言って有頂天になってのぼせあがるも危険なことですし、
また、少し悪いことが続くからといって無暗に落ち込んで、無気力になることも、
これもまた、馬鹿げたことです。
善い事が続いている時も、悪いことが続いている時も、是非、今一度、このお話を思い出して下さい。
私は、最近の世相を見てつくづく感じています。 なむあみだぶつ合掌

◎ 今日の一日は 二度とやり直しがきかない一日です。
◎ 昨日の事が気になる 明日の事が気になる今な私はどうですか。
◎ 太陽や大地や水の恵みを受けてお米や魚の命を頂き生かされて生きている私。
◎ 思いをこえたものを 思い通りにしようと思うから この世の中が地獄になる。
◎ 仏さまが 手を差し向けて下さっているのに背を向けている私。
◎ お陰様で生かされて生きている 見えない「かげ」の力で。
◎ 人間のいのちに輝きあれ 人の世にいのちのkが焼きあれ。
◎ 本当の自分に出会えない 人生はむなしいです。
◎ 愚痴が出た時 腹が立った時 悩みが解決できな時その元を聞いてみる。
◎ 人間の命に輝きあれ 人の世に 命にぬくもりあれ。

一口法話 平生業成 (へいぜいごうじょう)
じゃによって 常が大事ぞ 年の暮れ
お正月や、お正月やと言うている間に花の春が来て、桃や桜や言うている間に梅雨
梅雨が明けるともうそこに暑い暑い夏が待っている。
やれお盆や地蔵盆や屋と言うている間に秋が来て、紅葉を見に行く間もありませんわ、と
言うている間に木枯らしが吹いて年の暮れが来る。
その時になって今年はなにも出来なんだ、何とか正月までには間に合わさなければと慌てふためく。
これが私達の毎年送る年中行事のように思われます。
じゃによって 常が大事ぞ 年の暮れ
この川柳は誰がつくられた物か知りませんが、実に私達に平常の心がけを教えてくれている川柳です。
日々めさきのことにのみ目がくらんで、肝心な物大事なことを忘れている私達。
年の暮れになって慌てている私に”年の暮れになって慌ててもあきまへん。
そやさかいに。、平生が大事でっせ”と教えてくれている。
。
私達は命の終わる瀬戸際になって地獄行きか、極楽行きかと慌てふためく事の無いように
平常に仏さまのみ教えを聞かせて頂き、常に仏さまの大きなお慈悲の心が、
私にふりそそいで下さっているのだと、仏さまのおまもりを信じお念仏を喜ばせて頂く時
いついかなる時でも『命終わる時 彼の土(阿弥陀様のお国浄土)へは参るべきなり』(歎異抄)と
安心させて頂けるのです。
じゃによって常が大事ぞ年の暮れ
平生業成(平生業場)のみ教えを仰ぐ私たちの味合う言葉です
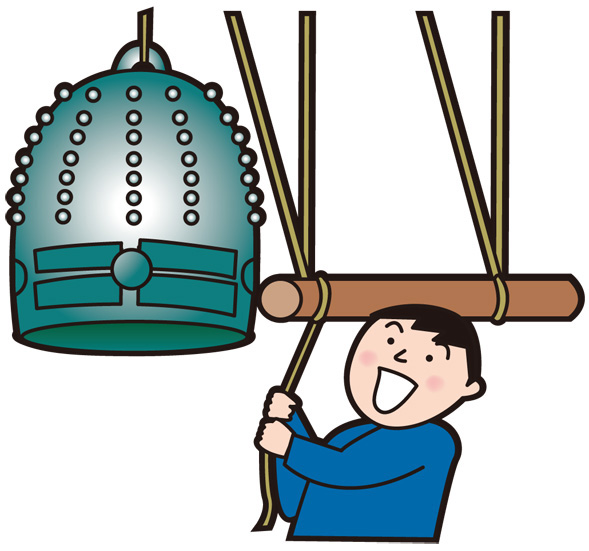
◎ いのちほど大切なものはないと言いながら 今日もその命を頂いて居る。合掌して「頂きます」
◎ 善事と知りつつ成し難く 悪事と知りつつ避け難い。
◎ 「私はウソをついたことが無い」のセリフで 嘘つき大会で優勝したと言う話。
◎ 自称善人が消えてくれると 悪人だって消えるかも。
◎ 自分流の物差しで計算したものに 本当の答えは出てきません。
◎ 念仏者の往生は永眠や他界するのではなくて アミダさまのお浄土に往き仏と成るのです。
◎ 人生は横断歩道の様に鵜危険一杯ですが、 信号に従えば安心して歩けます。
◎ 一緒に泣いてくれる人が有れば 救われます。
◎ 南無阿弥陀仏は煩悩具足の凡夫を 無条件で救て下さる如来さまです。
◎ 水・空気・星や太陽の輝く世界 人間だけのものでは無いはずです。
一口法話 苦 楽 (くらく)
一水四見と言うたとえが有ります。。
今、水が有るとして、ガキはこれを火と見ます。
魚はこれを自分の住と見、人間はこれを水と見る。仏さまは、これを瑠璃(るり)と見る
というのです。
同じ一つの対象も、見るものの心によって、違ったものに見えると言う事であります。
このごろは流行りませんが、清貧と言う言葉が有ります。
清貧を楽しむ、貧乏という一つの状況に置かれた場合とみる、
、貧乏は苦と見る人は多いでショウガ、貧乏なななkにも楽しく暮らしt5営る人もいるはずです。
数億の富を抱いている人の家庭でもは門の絶えまの無い場合も有るでしょうし、
今夜の糧に汗して働く人々にも家族が一つ心で笑い声のあふれる家庭も有るのです。
このように、境遇なり外にあふれた除隊そのものが、そのまま人間にとって苦しみとか
楽しみであると決めてしまわずに、むしろ、境遇をうけとるこころによって、
その人の幸不幸、九楽が決定する物だと言う事実に気づかねばなりません。
仏教ではオレがと言う、とらわれの心(執着)苦を招く原因であると教えて居ります。
◎ 救いの中に有る限り 希望はあっても絶望はない。
◎ 現在が救われると 過去も未来も救われる。
◎ 鬼は 世間ではなく自分の中にある。
◎ 穏やかな笑顔と優しくて暖かい言葉。
◎ 明るい町づくりは 先ず挨拶から
◎ アスハ。有難う。すみません。ハイは人の心を暖かくするし自分も気持ちが良い。
◎ この人といると 気持ちが暖かくなると言われるような人になりたいなぁ。
◎ 言うた人は忘れて居ても 言われた人は覚えている 良い事も悪い事も。
◎ した人は忘れて居ても された人は覚えている 良い事も悪い事も。
◎ たった一言が人の心を暖かくする。たった一言が人の心を暖かくする。
ひとくち法話
人 生 の 羅 針 盤
皆さんのお家にお仏壇が有りますか?仏壇の無い家庭は空き家と一緒だと言われています。
それは主人が居らない。私たちは主人と言いますと、家庭の主人はお父さんと考えて居ますが、
仏教では、主人は仏さまだと言ってます。
仏さまが家の主であります。
ですから、生活の中に仏壇が無いと言う事はそれでは本当の生活が出来ない。
仏さまと言う主を中心にして生活をする。
私たちの生活の中には悲しい事も有り、また嬉しい事もあります。
仏教では「人生は苦なり」と申しますが、思うようにいかないと言う事も娑婆の世界です。
そこで、私の心のよりどころ、そのより所を仏壇に求めます。
仏壇は決して先祖を祭るのではありません。
最近の人は仏壇と言うとご先祖を祭っておるのだと考えて居ますが、
仏壇は先祖では有りません。お仏壇は南無阿弥陀仏なのです。
南無阿弥陀仏と言う事は、私達を本当に生かして下さることを言うのです。
生きるより所を与え死の帰する所を明らかにすると言う事が仏さまであります。
そのほとけさまを、家の中心にご安置するということは、考えてみますと、主が定まると言う事です。
その主は私達の家庭の中心であり、そして、私m達の生活を色々と方向付けて下さいます。
船に羅針盤が有りますが、その羅針盤が無かったら方向は定まりません。
仏壇と言う人生の羅針盤が私達の生活の中に有ると言う事はまことに幸せな事で有ります。
困った時は仏さまと相談しながら生活をすると言う事が最も大切な事であります。
仏壇は無くなった人を祭るのではなくて、亡くなった人をしのばせて頂くときに亡くなった人を活かす。
そういう仏に私達は今遭わせていただくのであります。
仏壇は家庭の中心で有ることを忘れてはなりません。
大阪北御堂編ー真宗三分間法話 聞こえますかより

◎ 十人子を養う父が有る一人の父を養い得ない十人子もある 法句
◎ 浜までは 海女も蓑着る 時雨かな 瓢水
◎ 有り難い・勿体ない・済まないと言う事を忘れている人は一番不幸です。
◎ 人の悪い所はよく見えるが、自分の悪い所は気が付かない。
◎ 満足を知らないものは、如何に富に恵まれていても心は貧しい。
◎ 真実の信を得る人は心に喜びが多い。
◎ 亡くなった人が迷うと言っていると言うあなたの心が迷っているのです。
◎ 浄土は言葉の要らぬ世界・人間の世界は言葉の必要な世界・地獄は言葉の通じない世界
◎ 念仏して五欲の暑さ忘れよう。
◎ 浄土を願う人は浄土を作る人です。
◎ 誰にでも似たような悩みがある。誰にでも隠された涙が有る。
そこにかみしめられる人生の味 ひそかなる仏さまの声。
一口法話 馬の耳に念仏
念仏とはもちろん「南無阿弥陀仏」なむあみだぶつです。有り難いお念仏であっても馬に聞かせても有り難さは分からない。
それと同じでこちらがいくら忠告しても相手がそれを聞き流してしまってなんのききめのないときにこの「馬の耳に念仏」という・
浄土真宗のご開山親鸞聖人はお念仏は私達が自分の自由意思でもって称えるものではない。
念仏を唱えたいから称える、称えたくないから称えないと言うのでは人間のわがまま勝手が認められているわけだ
しかも、念仏を唱えたものを好かねばならないとしたら、阿弥陀仏は人間のわがまま勝手の奴隷になってしまう。
それでは、自動販売機と同じだ。自動販売機は、お金を入れた者には品物を出さねばならない。
お金を入れるか入れないか相手の自由でいれられたばあいには必ず品物を出さねばならぬのだから
自動販売機に自由はない。お念仏を唱えるか、称えないかを人間の自由選択に任せてしまえば
阿弥陀仏はまさに自動販売機になってしまうわけだ。
それではおかしい。…と言うのが親鸞聖人のお考えである。
そこで、親鸞聖人のお考えは、私達が有る時、お念仏を唱えようというきになる。実はそれがすなわち
阿弥陀仏が我々に対する働きかけである。と
私達は自由選択でお念仏を唱えているのではない。
お念仏を唱えようと言う心そのものが、阿弥陀仏の不思議な(我々の考えの及ばない)力によるものである。
したがって、お念仏を唱えようと言う心が起きたその時、すでに私達は阿弥陀仏に救われているのだと仰っています。
その後のお念仏は救われている喜びと感謝のお念仏「南無阿弥陀仏なのです。
仏教語辞典ひろさちや著より